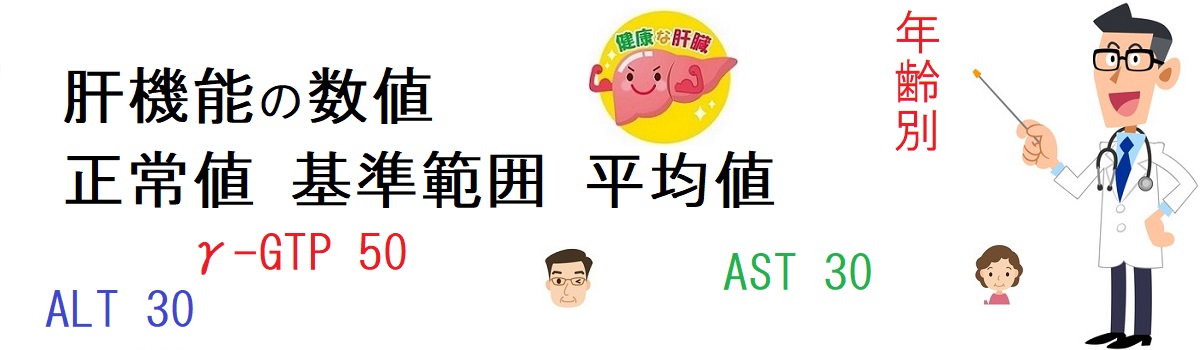⌛ 読み時間:3分
ヨーロッパでは「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあり、トマトはそれだけ体に良い食べ物という意味で使われてきました。
そしてトマトは、2012年2月京都大学のマウス実験の結果、脂肪肝や高中性脂肪血症が改善するという医学的なエビデンスも獲得しているのです。トマトは肝機能障害を予防または改善する成分を多く含んだ肝臓に良い食べ物なのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━

・抗酸化作用UPリコピン
・脂肪肝と中性脂肪⇘グルタミン酸
・アルコール処理能力UP⤴ナイアシン
・2012年 京都大学マウス実験🐀13-oxo-ODA(13オキソODA)の発表
トマトと言えば、「リコピン」。「リコピン」と言えば、「抗酸化作用」です。
抗酸化作用とは、ストレスなどで発生する活性酸素を排除する作用です。この活性酸素は人間の各臓器の細胞を破壊し、機能障害を引き起こす元凶となります。
特に肝臓は、活性酸素に極めて弱い臓器なので、活性酸素を出来るだけ減らせば、肝臓が元気を取り戻す可能性が高くなります。そこで肝臓に良い食べ物トマトの登場となります。
トマトのリコピンが持つ「抜群の抗酸化作用」が、弱った肝機能を回復させてくれるのです。トマトは赤ければ赤いほどリコピンが多いので、肝臓に良いトマトを選びたい時は、出来るだけ赤いトマトを選ぶのがポイントです。
グルタミン酸は、内臓脂肪(脂肪肝)の予防や減少、中性脂肪を減らす作用を持っています。肝細胞の30%が脂肪で覆われると「脂肪肝」と診断され、肝機能障害の出発点に立ってしまいます。
脂肪肝は、高糖質な食事や飲酒習慣などで増えた中性脂肪が肝臓内で変化したものです。トマトは多くのグルタミン酸を持ち、脂肪肝や中性脂肪を代謝します。
豊富なリコピンとグルタミン酸で肝臓病の元凶をシャットアウト!トマトは間違いなく、肝臓に良い食べ物と言えるでしょう。
トマトにはもう一つ「ナイアシン」という成分を多く含んでいます。
ナイアシンは、肝臓の仕事の一つである代謝(糖質や脂質)のサポートをする物質なので、肝臓には必要不可欠な成分と言えますが、なかなか食べ物で十分な量を摂取するのが難しい成分でもあります。
また、ナイアシンは、肝臓のもう一つの仕事である解毒作用(アルコールなど)があり、お酒を分解する際に発生するアセトアルデヒドの解毒を強力に助けてくれます。
つまり、トマトの持つナイアシンは、肝臓の仕事「代謝&解毒」というメインの仕事の重要な助っ人になるのです。ですので、肝臓に良いトマトを食べて、肝臓を保護するようにしていきましょう。
・2012年2月 京都大学マウス実験🐀13-oxo-ODA(13オキソODA)の発表
2012年2月、京都大学は、「トマトに含まれる13-oxo-ODAを肥満マウスに与え臨床試験を行った結果、脂肪肝や高中性脂肪血症の改善が顕著に見られた」と発表しています。
トマトはリコピンやナイアシンだけではなく、2012年2月以降この13-oxo-ODAという新しい成分による医学的なエビデンスを持つようになりました。トマトは間違いなく、肝臓に良い食べ物と言えるでしょう。
肝臓に良い食べ物と対策を知ろう
━━━━━━━━━━━━━━━━
今日は、肝臓に良い食べ物トマトの成分や脂肪肝や中性脂肪への効果などをまとめました。皆さんの肝機能の数値が正常値へ向かうよう期待します。