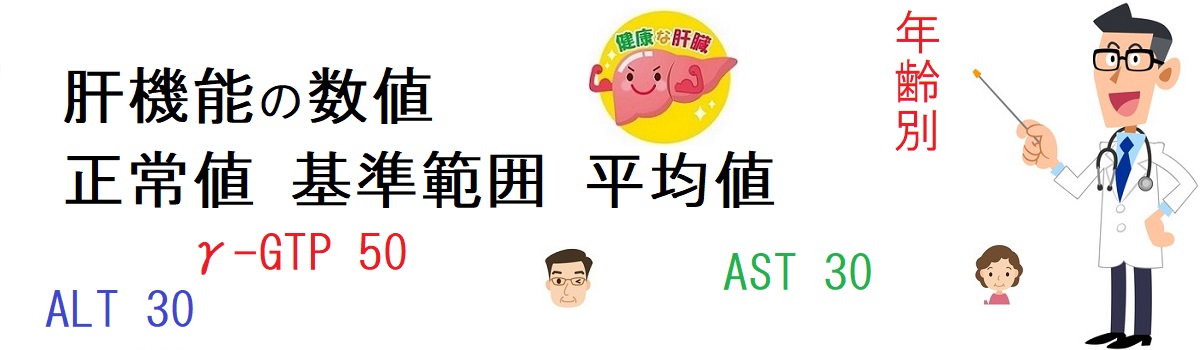⌛ 読み時間:3~4分
肝臓に良い食べ物の王様と言っても良いかもしれません。今日は大豆の概要、大豆が持つ肝機能を回復させる成分、そして大豆製品である納豆、枝豆、豆乳についてまとめておきます。

・畑の肉「大豆」
・愛媛大学のマウス実験(サポニン)
・納豆~ビタミンB2&ムチン
・枝豆~ビタミンC&コリン
・豆乳~低糖質&高たんぱく質
大豆は「畑の肉」と呼ばれ、良質な栄養素が詰まった食べ物の王様と言える食品です。「肉」は、動物性脂肪や高カロリーになりやすいなどの問題がありますが、大豆はいい事だけで体に害となるような問題はない食品です。
もちろん大豆は、肝機能障害を回復させる栄養素も多く含んでいます。良質な大豆たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、植物性脂肪など、肝臓に良い栄養素がバランスよく摂取出来るのです。
また大豆は、糖質やカロリーが低く、糖尿病を患う方でも、高血糖のリスクがなく、中高年にはありがたい食べ物でもあるのです。大豆の唯一の問題点は、大豆そのままでは食べにくい食べ物という点だけです。
後ほどお話する大豆の加工品(納豆、枝豆、豆乳など)を上手く食べるようにして、肝機能を回復させていきましょう。
2009年11月愛媛大学医学部のマウス試験の結果、「大豆のサポニンは、高コレステロールと高中性脂肪を減少させる」と発表しています。肝臓で中性脂肪が変化したものが脂肪肝となります。
また、大豆サポニンは抗酸化作用を持ち、肝機能の数値であるALT(GPT)の上昇を抑制する事も確認出来たとしてますので、大豆は医学的な根拠も獲得しているのです。
肝臓に良い大豆。「毎日食べる」で間違いない食べ物です。納豆、豆腐、豆乳などを毎日日替わりで食べて飽きないようにすると続けやすいですね。
納豆は発酵によりビタミンB2が大豆の2倍になり、脂肪肝への効果も倍増します。また納豆といえばあのネバネバですが、あれはムチンという成分で、アルコールの吸収をゆるやかにする作用があります。
肝臓の仕事の一つがアルコールので解毒作用ですから、納豆によってアルコールの解毒を急がずに済むようになり、肝臓の負担軽減につながります。
<注意点>
血液をサラサラにする薬「ワーファリン(抗血栓薬)」を服用中の方は、納豆を食べてはいけません。納豆に含まれるビタミンKは血液の凝固作用、ワーファリン(抗血栓薬)は血液サラサラ作用となり、薬の効果が減少してしまう可能性があるからです。
・枝豆
枝豆には、脂肪肝を予防したり、脂肪を代謝する成分である「コリン」がたくさん含まれています。ただし、もぎたての枝豆にコリンが最も含まれているので、出来れば枝豆の旬である8月に食べて頂きたいです。
また、枝豆は大豆に比べてビタミンCがとても豊富な食べ物です。大豆100gのビタミンCが0mgに対して、枝豆100gのビタミンCは何と30mgも含まれています。
ビタミンCは、抗酸化作用と活性酸素の除去、そして免疫力アップという肝臓にとても良い栄養素です。ぜひ食べるようにしましょう。
余談になりますが、私は8月もぎたて「だだちゃ豆」を愛しています。8月=夏本番・・・ビールに最高のおつまみですね・・・肝機能障害の方もたまには息抜き?もいいかもしれません。
最後は、食べ物ではありませんが豆乳です。やはり大豆、納豆、枝豆は、ある程度の量を食べる必要がありますが、一日コップ1杯(200ml)の無調整豆乳なら簡単に飲めますよね。
例えば、キッコーマンの無調整豆乳(200ml)の栄養成分をいくつか抜粋すると、115kcal、たんぱく質9.1g、大豆サポニン80mg、イソフラボン56mg、炭水化物3.2g、という感じになっています。
カロリー115kcalや炭水化物3.2g(糖質は1~2gほどと推測)は牛乳より低いですが、たんぱく質は牛乳の7gと比べて2g以上多いです。やはり肝臓に良いのは豆乳の方です、低糖質で高たんぱく質の豆乳を飲むようにしましょう。
肝臓に良い食べ物と対策を知ろう
━━━━━━━━━━━━━━━━
今日は、肝臓に良い食べ物大豆、納豆、枝豆、豆乳をまとめました。大豆は最強の肝臓に良い食べ物です、毎日の食生活に取り入れて、肝機能の数値を正常値へ向かわせましょう。